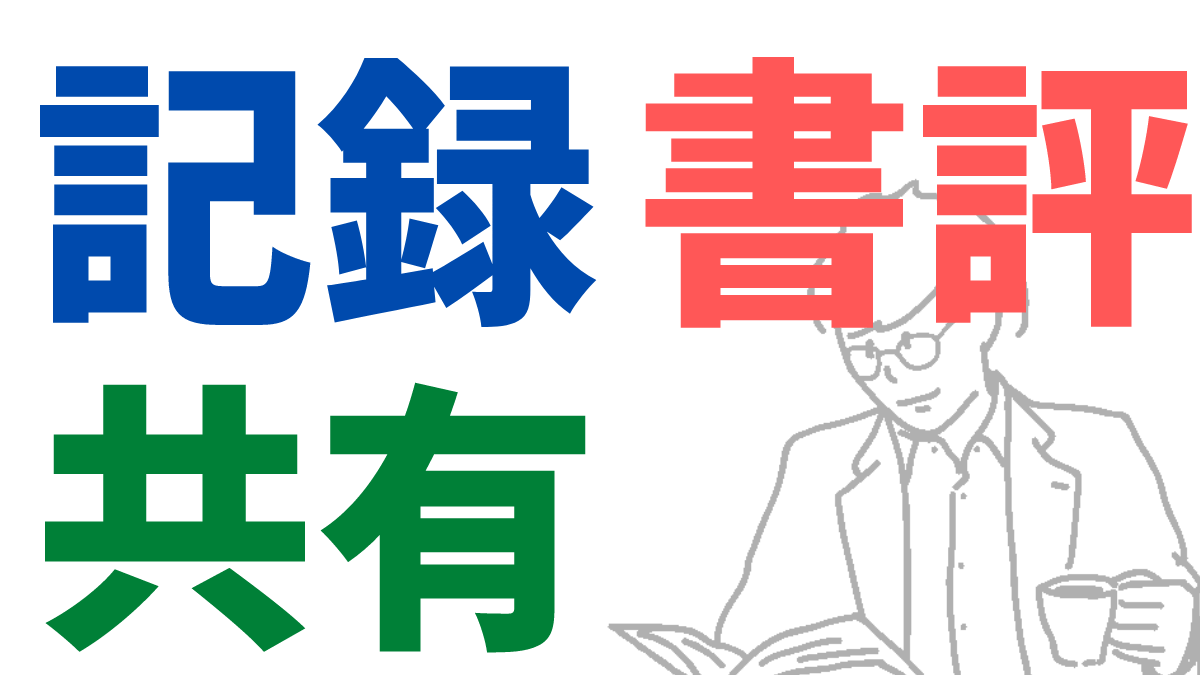
インスタやツイッターなど、今たくさんのSNSがありますが、読書のためのSNSも多数リリースされています。
この記事では読書SNSそれぞれの特徴をご紹介!
読書SNSを使えば、
- 読書記録を管理して、読んだ本を忘れない
- 同じ趣味の人が読んでいる本を参考にできる
などのメリットがあります。
読書SNSはメジャーなものからマイナーなものまで、かなりの種類が世に出ているのですが、以下ではユーザー数や知名度を考慮して5つ選んでいます。
それぞれの特徴を見て、ぜひ自分にあったものを選んでくださいね!
- 実はSNS的に使える「Amazonレビュー」
- 読書量の管理機能を重視するなら「読書メーター」
- 課題図書で新しい本に出会える「読書ログ」
- コミュニケーション要素が強い「ブクログ」
- 新刊のチェックなら「Stand」
- 【番外】noteやブログで書評を書くのもおすすめ
- 【番外2】書評を書いて、お金が貰えます「ブックレコメンド」
- もっと探す、運命の本を
関連記事:ネットで本を買うならどこ?本の通販サイトを上手に使って得する方法!
実はSNS的に使える「Amazonレビュー」

おなじみAmazonのレビュー機能では、その人がレビューしたアイテムの一覧ページ(プロフィールページ)があります。
例えば、あなたの好きな作家の小説をレビューしている人のプロフィールページをチェックしてみましょう。
おなじみ趣味の人のおすすめ作品を知ることができます。
またプロフィール機能には「著者をフォローする」便利機能もあります。
お気に入り作家の最新作を逃さずチェックできるので、読書家の人はぜひ活用してみてください。
読書量の管理機能を重視するなら「読書メーター」

読書SNSの基本的な機能「読書記録」をつけるを重視するなら読書メーターがおすすめです。
読書メーターなら、読んだ本の量をグラフ化できるので、自分がどれくらい読んだか一目瞭然です。
月ごとの冊数・ページ数も記録できます。
「みんなのつぶやき」というコーナーはSNSのような感じで、他のユーザーのつぶやきを見ることができます。
トップページを見ると、小説、コミック、ライトノベルなどに分類されており、これらのジャンルのレビューが盛り上がっている(盛り上がる仕組み)のようです。
逆に言うと、ビジネス本だけを読む人には少し物足りないかもしれません。
また読書メーターは献本プレゼント企画も多数開催しており、運がよければ無料で本がゲットできちゃいます。
もちろん献本ですから、ちゃんとレビューを書く必要がりますよ。
読書メーターは記録機能はもちろんのこと、SNS、献本と機能が充実しており、総合力の高い読書サービスと言えそうですね。
ウェブ、アプリ両方から利用できます。

課題図書で新しい本に出会える「読書ログ」

読書ログは、
読書ファンが集まる読書レビューサイト
と銘打っているだけだって、他人のレビュー(書評)が見やすいデザインになっています。
レビューに対してさらにコメントもできるので、ユーザー同士で感想を言い合って盛り上がることができますね。
ですから、自分が読んだ本の感想を誰かと共感したいとか、あらかじめレビューを読んで購入前の参考にしたいといった人におすすめです。
また、月ごとに違う本をみんなで読む「課題図書」という企画も特徴的。
課題図書に選ばれるのは、小説だけでなくノンジャンルのようです。
また新刊に限らず、編集部が選んだユニークな本や過去の名著など多岐にわたっています。
ちょっと違った視点から新しい本に出会いたい人には楽しい企画です。
読書ログはウェブサイトのみの展開となっています。
コミュニケーション要素が強い「ブクログ」

ブクログはアプリやサイト上で自分の本棚を作り公開する、というコンセプトのサービスです。
会員数は100万人を突破しており、この手のサービスでは老舗の部類に入ります。
読んだ本の背表紙が画面にズラッと並ぶデザインが特徴的で、まさに”本棚を公開”といった様相を呈しています。
記録が大量になると、PCやスマホ画面のタイトルの文字だけを目で追うのは少し疲れますよね?
ブクログはこのように表紙が並ぶデザインなので一覧性が高く、自分で見直すときも便利ですし、他のユーザーの本棚をのぞくのも楽しいです。
他のユーザーをフォローすると、タイムラインに更新が羅列され、SNS機能も完備しています。
ユーザー数も多いですし、SNSとしてコミュニケーションを楽しみたい人にはいちばんおすすめできるサービスです。
ブクログはウェブとアプリの両方から利用できます。

新刊のチェックなら「Stand」
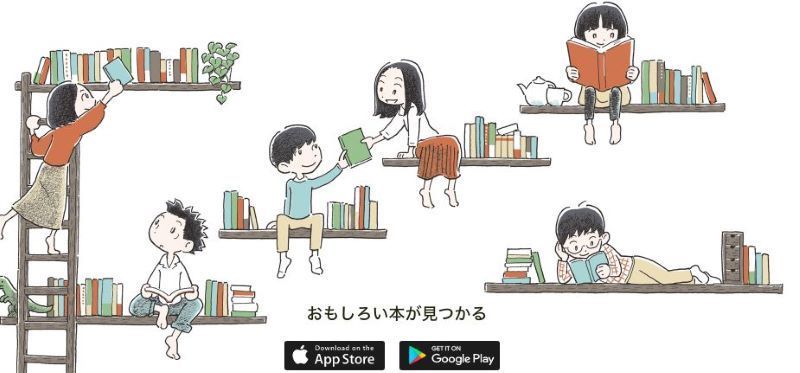
StandはAppleベスト2015アプリ、文化庁メディア芸術祭 審査員推薦作品に選ばれています。
読書記録、ユーザーフォローなどは他のサービスといっしょです。
特徴的なのは試し読み機能。 毎月、約3,000冊の新刊が「試し読み」ができるようになっており、立ち読み感覚で本を精査することができます。
新刊チェッカーとして他のサービスと併用するのもアリかもしれません。
Standはウェブ、アプリ両方から利用できます。(ただ見た感じ、アプリからの利用が前提になっているようです)

【番外】noteやブログで書評を書くのもおすすめ
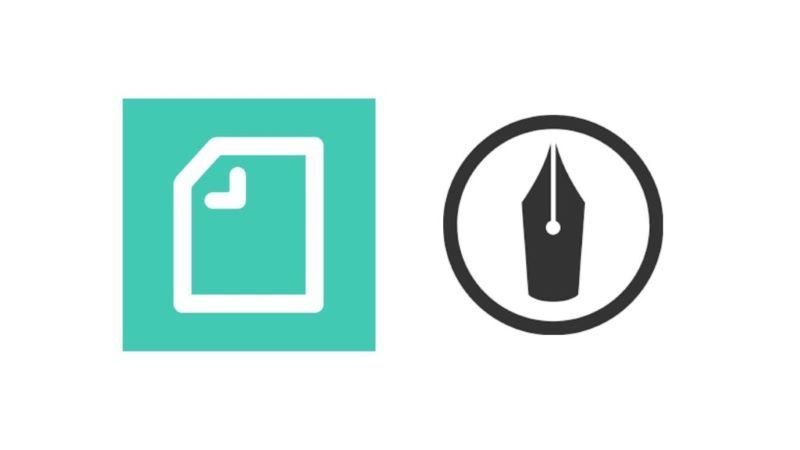
書評や本の記録だけでなく、日常の日記やちょっとした話題もネットに書きたいという場合があると思います。
たとえば読書家の人なら、本を読みに出かけたカフェの話や、お気に入りのブックカバーの紹介など、誰かと共有したいことってありますよね。
そんな時はnoteやブログがおすすめです。
noteは今、いちばんかんたんにネットで文章が書ける場所といっても良いでしょう。
ツイッターやフェイスブックのようにサクッとアカウントを作成でき、アプリからでもウェブからでも簡単に文章が書けます。
余分な装飾や設定がないので、執筆に集中できるのがメリットです。
また2020年7月時点でUU(ユニークユーザー、実際に利用しているユーザー数)が4000万人を突破しており、もしもおもしろい記事を書いたらバズる可能性も高いSNSです。
ですから単なる読書記録だけでなく、多くの人に自分の文章を読んで欲しい人(ライター志望の方など)だったらnoteで書評を書いてみるのもおすすめします。
noteとは違うブログサービスで書評を書くのも選択肢のひとつです。
いわゆるブログはnoteと違い、ブログ(サイト)タイトル、サイトデザイン、文字装飾、カテゴリーなど自由にデザイン、設定をすることができるのがメリットです。
例えばZINEとか作ることが好きな人だったら、いろいろと自分好みにサイトデザインをいじられるブログの方が楽しいのではないでしょうか?(逆に「ITがめちゃ苦手」ならnoteがおすすめです)
ブログサービスはさまざまありますが、コミュニティがあり比較的に読者がつきやすいブログサービスはアメブロとはてなブログかなと思います。
はてなブログは、はてなブックマークというソーシャルブックマーキングサービスと合わせて、独特のコミュニティが形成されており、比較的長文を読んでくれる文化が根付いています。
またデザインもアメブロに比べてシンプルなものが多いですね。
もちろん先ほど紹介した読書SNSとnote(ブログ)を併用するのも良いと思います。
ブクログのフォロワーさんをnoteへ…noteのフォロワーさんをブクログへ…などお互いの宣伝として利用して、読んでくれる人が増えていくと楽しいですよ。
ぜひ読書SNSと合わせて検討してみて下さい。
それぞれのサービスをさらに詳しく解説している関連記事も参考にしてみてください。
関連記事:「ネットで文章を書いて投稿、公開する」なら、どのウェブサービスを使うべき?おすすめ5選
【番外2】書評を書いて、お金が貰えます「ブックレコメンド」
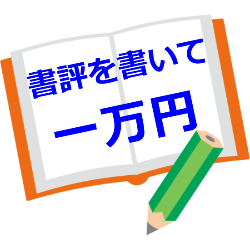
どうせ書評を書くのなら、お金がもらえたら嬉しいですよね?
ブックレコメンドという人気書評サイトをチェックしてみて下さい。
常時、寄稿を募集しています。
ブックレコメンドはライター本人の感性で「この本を読んだら、次はこれを読もう!」と、次に読む本をおすすめする書評が掲載されたサイトです。
Amazonのように機械的にレコメンドされるわけではなく、ちゃんとその本を読んだ人が人力でレコメンドしてくれてるので説得力が違う。
そのスタイルが評価されて、今では月間70万PVの人気サイトになっています。
寄稿報酬はもとより、自分の書評を多くの人に読んでもらうチャンスです。
報酬の詳細などはブックレコメンドのサイトをご覧ください。
もっと探す、運命の本を
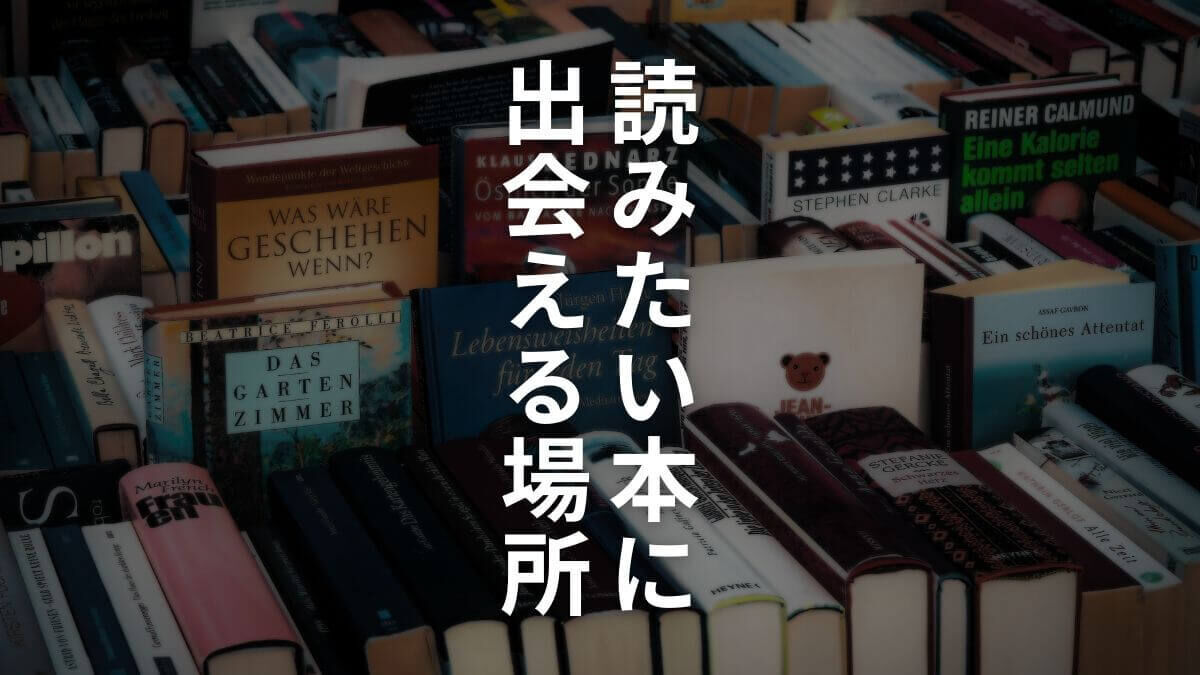
読書SNS以外にも、次に読む本を探す参考になるサイトやイベントをまとめています。
「今のじぶんに必要な本になかなか出会えていない…」
そんな読書家の人は、ぜひチェックしてみてください。
関連記事:次はなに読む?いろいろな本の探し方、出会い方まとめ

