
スマホ依存に関する本をたくさん読んだのでご紹介します!
上から「読みやすい」順に並べました!
「似たような本をたくさん読む必要あるの?」
と思うかもしれません。
しかしこと「スマホ依存」に関して言うと、むしろ読まないとダメな気がします。
正確に言うと、
「強力なスマホ依存という病に対しては、定期的に薬となる本を読まないと対策するのはムリだ」
ということ。
なんせスマホはいつでもポケットに、カバンに潜んでいるものです。
1日1回も見ないなんて誰しもできないのでは。
だから以下の本で定期的に自分を見つめ直す機会を持つことが、多くの人って現実的だと思うのです。
ちなみにスマホの文章に慣れ過ぎていると、長文を読むことができなくなるそう。
ですからこの記事では「読みやすい」順に並べました。
「スマホの使い方を見つめ直したい」
「我が子にスマホをどう使わせるか、悩んでいる」
そんな人もぜひチェックしてください。
- もっともシンプルでわかりやすい『スマホ脳』
- ニュースにはデメリットがある『News Diet』
- 生物学的視点から人間とスマホの相性を探る『スマホを捨てたい子どもたち』
- 哲学としての脱スマホ『デジタル・ミニマリスト』
- SNSの依存テクノロジーを紐解く『僕らはそれに抵抗できない』
- 依存の原因ドーパミンを詳しく『もっと! 愛と創造、支配と進歩をもたらすドーパミンの最新脳科学』
- 本を読んでわかった「スマホ依存の対策」をまとめました
もっともシンプルでわかりやすい『スマホ脳』

子どもにスマホを使わせるべきか…。
悩んでいるなら、いち早くこの本を読むべきです。
スウェーデンの精神科医、アンディ・ハンセンの著書『スマホ脳』は、そのタイトルから想像させるとおり、現代のスマホ社会に警鐘を鳴らす本。
あらゆる「スマホ依存」の本でも、読んだ『スマホ脳』は一番読みやすい内容です。
関連書籍と重複する内容は多々あれど、エビデンス(根拠)と主張がシンプルに論じられており、とても腑に落ちやすい。
また時折
「iPhoneの発案者であるスティーブ・ジョブスですら、我が子にはiPadを見せなかった」
といったセンセーショナルなエピソードを混ぜ込むことで、つよくスマホの危険性を訴えかけることに成功しています。
人がスマホを見てしまうのはドーパミンが関係している。
ではドーパミンとはつまりどんな物質で、なぜ人間に必要なのか?
生物学的観点(つまり人類として)から説明しています。
例えば、ドーパミンは「○○かも」というシチュエーションに遭遇した時、いちばん放出される脳内物質だそう。
「1km先にリンゴがあるかも」
その時、その場所に向かわせるためにドーパミンが発せられます。
「確実にある」「確実にない」という場合はドーパミンは出ない。
確実にあるなら、お腹が空いた時に行けば良いし、ないなら行かなくてもいいわけです。
基本的に食物が不足していた原始において、「○○かも」というシチュエーションは必ず確かめる必要がありました。
だから「○○かも」でドーパミンが出る。
また「新しい情報」に対してもドーパミンが出るそう。
1kmでリンゴをゲットしたら、次はまた新しいリンゴを探しに行く必要があります。
だから「誰か他にリンゴ知らない?」と新しい情報を求め始めます。
ひるがえって現代のスマホ社会に戻ると、スマホとはつまり
「新しい情報」が「あるかも」よ?
と、常にポケットから訴えかけてくる存在なわけです。
そいつを積極的に気にする(ドーパミンが出る)ように、わたしたちの脳は進化してきました。
だから、気になって気になってしょうがない。
結果的にスマホ以外の事柄に対して注意散漫になり、いろいろと弊害が出てくると。
これはスマホのデメリットのほんの一部で、本書ではもっと詳しく語られています。
とりわけ子どもたちの脳の成長にどんな影響を及ぼすのか。
第7章「バカになっていく子供たち」は特に危機感を持って読みました。
しかし今、わたしはブログでスマホ依存に関する本を紹介して、あなたはスマホでこの記事を読んでいるのではないでしょうか。
なんだかその風景はちょっと滑稽で矛盾しているように思えませんか?
「スマホがダメなら、ブログなんて書くなよ」と。
それはホントその通りですよね。
しかし今や、誰もがその矛盾に答えていかないといけません。
近年は大手マスメディアから、インターネットの世界へ急激に広告費が流れています。
その金額は既に逆転し、インターネットメディアの方が多くなりました。
つまりビジネスの主戦場がスマホの中に移ったということ。
誰しもが食べていかないといけないわけですから、全ての大人はスマホのなかでビジネスすることを避けて通れません。
おそらくわたしたち世代がこの矛盾にどう答えていくかで、20年後の未来が決まっていくでしょう。
「消費者」としてスマホを手放すことは、実は難しくない。
しかしこと「生産者」になると難しい…。
自分は依存したくないけど、人を依存させるのはOK?
とりわけメディア従事者においては、その問いにどう答えていくべきでしょうか?
広い意味でメディアを手掛けている人たちも色んな道を模索しています。
SNSに迎合してバズを狙う人。
紙媒体に戦略的に撤退する人。
ネットの中で、あえてスローな発信を目指す人。
どれが正解かは今、言うことはできませんが、わたし自身はネットの中でスローな発信をしていきたいなと思っています。
個人的にこの『スマホ脳』はもっと売れて欲しい。
帯に「世界的ベストセラー!」と銘打ってありますが、書籍の世界でベストセラー(大ヒット)といっても、せいぜい100万部とか。
日本国民だけでも、1億人以上いますから、スマホに対する危機感はなかなかメインストリームになり得ないでしょう。
そこに一抹のさびしさを感じながらも、だからこそ気づいた人は積極的に矛盾して、問いを自分の中に持ち続けて欲しいなと思います。
これから依存するすべての子どもたちへ、これから依存させるすべての大人たちへ、この本を贈りたい。
その意味では、まさに「一家に一冊」おいていて欲しい本です。
ぜひ時間を作って読んでみて下さい!
ニュースにはデメリットがある『News Diet』

「ニュースは体に悪い!」
それだけを強烈に論じた一冊です。
著者は日本でも売れている『Think clearly』や『Think smart』を書いたロルフ・ベドリ。
彼はもう10年以上、ニュースを見ない生活をしているそう。
読むのは、長文の論考や本。
そしてそれでまったく十分だし、ニュースを読むことでかえって弊害あると、この本では明確に語っています。
本書ではたびたび
「あなたが1年間で見たニュースで、重要だと思うものを思い出してみよう」
と問いかけます。
わたしも考えてみると…いやぁ、これがまったく思い出せない(笑)
この時点でロルフの主張がほぼ正しいことを証明しているように思います。
ニュースに対して何かしらの「必要性」を感じて、わたしは日々ニュースを消費していた。
けれど、いざニュースで得た知識を現実に運用しようとしたら、これがまったくできない。
だとすればそれは本当に意味がないことですよね。
ロルフ曰く、ニュースのほとんどは自分の「能力の輪」の外にあると。
だからニュースで物事を知ったとしても、その事柄に何も影響を及ぼすことができない。
そればかりか、影響を及ぼせないことの無力感が、心の弊害になることを指摘しています。
きっと本当に世界を良くしようと思ったら、ニュースに時間と精神とお金を浪費するのではなく、自分の仕事や生業をいかに思いやりのあるものに変えていくかに苦心した方が良い。
心配しなくても世界はちゃんと繋がっていて、良い仕事が繋がって遠い人にも良い影響を与える気がします。
余談ですが、ミスターチルドレンの「彩り」という歌がそんな歌で、わたしは好きです。
「能力の輪」の考え方は「ミニマリズム」とも接近しているように感じました。
どちらも自分の手の中で納まることに集中することです。
News Dietは情報のミニマリズムとも言えるかもしれません。
現代はニュースのデメリットが極めて強調された時代です。
そもそもニュース媒体はとにかくニュースを見せることを第一に考えます。
それが商売ですからね。
その市場原理とスマホの相性は、悪い意味でばつぐん!
いつでも手の中にいるスマホがニュースを届けよう届けようと狙っています。
そういった情報環境を考えれば、わたしたち消費者側がニュースに対して距離をとらないことには、いつまで経ってもニュースが追いかけてくることになるでしょう。
本書で示されいる「ニュースの未来」も決して楽観できることではありませんでした。
この本は小気味よくニュースのデメリットについて論じています。
ともすれば「ニュースは絶対悪だ」と言っているように受け取ることができるでしょう。
しかし、それこそニュース的な情報の受け取り方だと指摘しておきたいと思います。
ニュース的とは一元的で、速報性があり、情報の根拠が脆弱なこと。
そもそもなぜニュースを避けるべきなのでしょうか?
それは物事に対する複雑性を回復するためです。
例えば「テレビは嘘ばっかり」という意見があります。
実際はテレビだろうがYouTubeだろうがSNSだろうが嘘はたくさんあるし、テレビにも良質なコンテンツはたくさんあります。
冷静に考えれば、プラットフォーム単位で断定するのはいささか無理がありますよね。
同じように「ニュースは悪!」と断じることは、大切な何かを見落としているかもしれません。
ニュースは悪かもしれない、でも本当にそうだろうか?良い面はないのだろうか?
そう考えることは非常に重要な思考だと思います。
実は「ニュースは悪だ!」という意見こそ、ニュース的な思考(断定的な主張)に毒された結果だと言えるでしょう。
ぜひこの本をニュース的思考で読むのはやめて欲しいと思います。
「ちょっと待てよ…」と立ち止まって、自分で考えて、この本から世界の複雑性を理解するように読んでみてはどうでしょうか。
とは言え…ニュースを見るのはやめた方が良いと思います(笑)
わたしもさっそくニュースアプリを削除しました。
「ないを言ってるんだおまえは…」と思ったかもしれません(笑)、
でも、
「ニュースは悪ではない、でも自分は見ない」
という立場は成立するでしょう。
そしてその方がニュースを悪だと断じる立場より、ニュースを是正する力学も働きやすい気がするのですが、どうでしょうか?
この本は、再読しやすいようにポイントをまとめた箇所があります。
そういった編集の本は普段本を読まない人にも読みやすいです。
ネットニュースに慣れると、長文が読めなくなるそう。
もしかしたらそういった人も想定して、読みやすい編集になっているのかもしれません。
生物学的視点から人間とスマホの相性を探る『スマホを捨てたい子どもたち』

スマホ依存に関する本を読んでいると「そもそも人間の脳は原始の時代から…」といった話題が頻繁に登場します。
脳みその進化には1万年かかるらしく、1万年前にもちろんスマホはないわけで、脳はスマホに適合するようにはできていないと。
と、なるとその原始の時代から続く人間の脳や本能についてより興味が出てきます。
現代において、その原始の脳の一端を見せてくれるのがゴリラかもしれません。
この本は京都大学総長で生物学者の山極寿一さんがゴリラやサルなどから得た「生物学的視点からみる人間の本質」とスマホを代表とする現代テクノロジーの齟齬(そご)を読み解いていく内容です。
単純に読み物としてもおもしろく、幅広く色んな人におすすめできる本です。
関連記事: 『スマホを捨てたい子どもたち』書評レビュー。ゴリラを見るとスマホのデメリットがわかる?
哲学としての脱スマホ『デジタル・ミニマリスト』
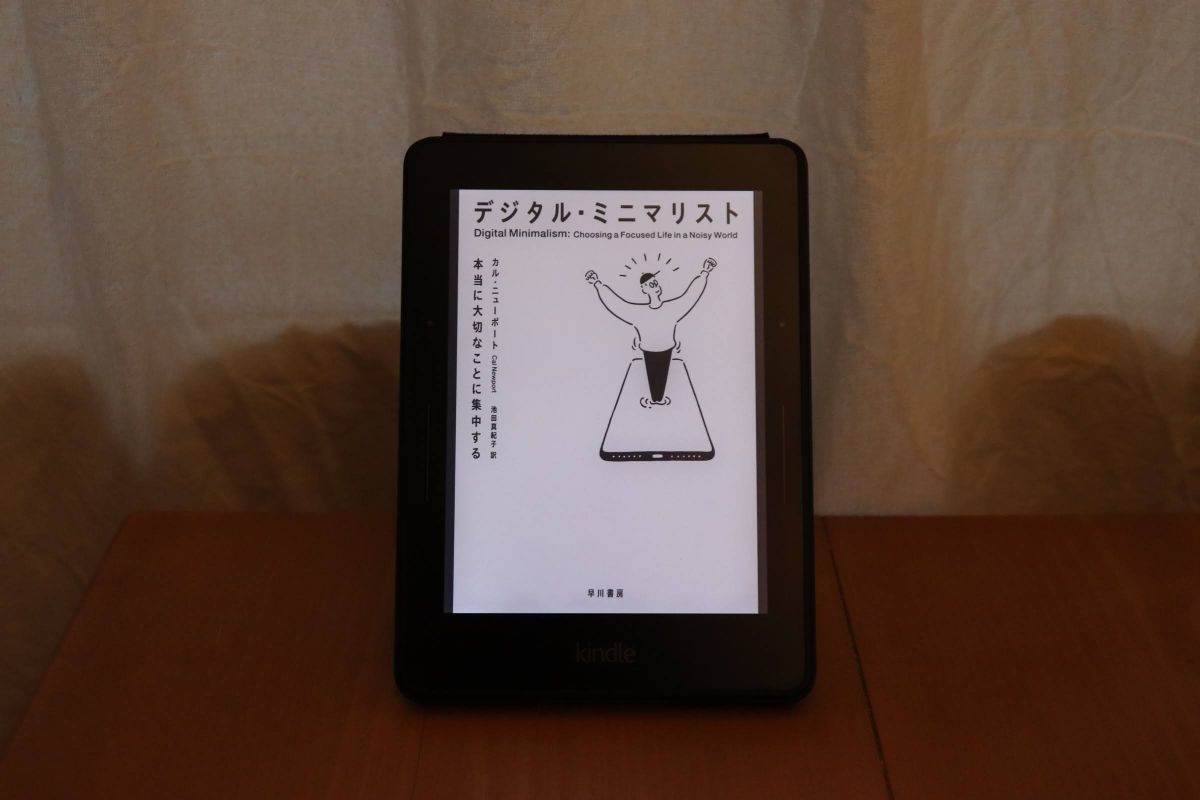
ミニマリストとはできるだけモノを持たないことを信条とする人。
それは生活における哲学だと言えます。
哲学があると何が良いかと言うと、環境が変化してもぶれないことです。
ミニマリストは山に行っても、海に行っても、どこに住んでも、自分の哲学でもって生活を構築していくでしょう。
それはきっと平穏につながります。
同じようにデジタルに対しても哲学が必要だろうと、この本の著者は主張しています。
言うまでもなく、新しいテクノロジー、新しいデジタル媒体は生まれ続けています。
これからも新しいものがいくつも登場するでしょう。
その時、わたしたち消費者は哲学を持っていなければ、その新しさに振り回され続けることになる。
哲学はある意味で「鉱山のカナリヤ」のように、その事柄を判断する材料になるものです。
著者が提唱する哲学が、タイトルのとおり「デジタル・ミニマリスト」であり、その構築方法を丁寧に解説しています。
なにかカタそうな本ですが、多くの人物と物語が登場するので、思ったよりも読みやすい本ですよ。
SNSの依存テクノロジーを紐解く『僕らはそれに抵抗できない』

主にSNSがどうやって依存の仕組みを自分たちのビジネスに取り入れているかを解説した本です。
いいね!ボタンが脳の○○を刺激する。
フォロワーは、リツイートは、タイムラインは…。
どれもこれもわたしたちの避けられない本能を刺激する仕組みを採用しています。
その事実をエビデンスを用いて徹底的に指摘しています。
ここまでくると、もうさすがにスマホを辞めたくなっているかもしれません(笑)
依存の原因ドーパミンを詳しく『もっと! 愛と創造、支配と進歩をもたらすドーパミンの最新脳科学』

「スマホ依存」の本を読むと必ず現れる言葉がドーパミン。
この本はスマホ依存だけでなく、ドーパミンにフォーカスをして専門的に解説している内容です。
この本でドーパミンを説明するために対になる概念が登場します。
それが「H&N物質」というもの。
ヒヤー&ナウの略で「今ここ」に集中する時に脳内で出される物質だそうです。
H&N物質の代表格がセロトニンやオキシトシンなど。
対してドーパミンは今ここではない未来や世界を想像させ、それに向けて行動させようとする物質です。
ポイントは「ドーパミンそのものは幸福感をもたらさない」ことと「ドーパミンとH&N物質は反比例する」ことです。
ドーパミンは「快楽物質」と表現されることがあります。
しかしこれは間違いで、ドーパミンが噴出されるときは、興奮こそすれど幸せを感じているわけではないそう。
むしろ幸せを感じている時はH&N物質が優位になっています。
ドーパミンは人を突き動かしはすれど、それが幸せかどうかはわかっていません。
そしてお互いに反比例しているがゆえに、ドーパミンが常時出ているとH&N物質が働かず、幸福感を味わえない。
例えば「あれが食べたい!」と思った時は、まさにドーパミン優位の状態です。
ですが、いざその食べ物を食べた時に「あ、あれも食べたいなぁ」と想像してしまうと、それはドーパミンの仕事なので、H&N物質が抑制されます。
結果的にあれだけ求めたいものを食べたのに、美味しさを存分に味わえず満足できなくなる。
この原理はなにか大きな教訓を読み取れそうな気がしますよね。
今、ここにないものを求めてばかりでは幸せにはなれず、目の前にあることを愛でることが必要。
ミスターチルドレンの歌詞のようですが(笑)、この本で紹介されている原理を読み解くとそう言えると思います。
この本はドーパミンとH&N物質の対立を軸に、恋愛、創作、発明、依存、政治といったテーマを紐解いていきます。
例えば恋愛では、ドーパミンはもちろん欲求を司り、H&N物質は友愛を司ります。
不倫してしまうのは、どっちが優位の人…?
ただ全体的にドーパミン VS H&N物質というカタチで論が進んでいきながらも、最終的には両者のバランスをとることを提案しています。
さらにわたしがこの本を読んで、話をややこしくさせていると感じたのは、ドーパミンが2種類あることでした。
ドーパミンは、直近の未来に訴えかける「欲求ドーパミン」と、遠い未来に訴えかける「制御ドーパミン」に分かれます。
例えば目の前に食べ物があったとして、「栄養だ!食べて補給せよ!」と言うのが欲求ドーパミン。
対して「食べ過ぎたら太るよ。我慢だ!」と言ってくるのが、制御ドーパミン。
制御ドーパミンは努力ドーパミンとも表現され、ドーパミンを持ってドーパミンを制すみたいな状況があり得るんですね。
逆に言えば、ドーパミンを一元化して制限しようとすると、努力もできなくなってしまうわけです。
ですから、H&N物質だけを優位にすれば平和だ、というわけではなく、必ず両立させる必要があると。
ただ結果として、今私たちの現代社会では、おおむねH&N物質を優位にするスイッチを入れるべきだろうと思います。
スマホ依存がある社会。
それはドーパミンスイッチを四六時中おされる社会です
情報分野だけでなく、町を歩けばコンビニ、ファストフードが溢れ、絶えずドーパミンを刺激してきます。
意識してドーパミンを制御しないことにはH&N物質がうまく出せなくなりそうです。
マインドフルネスなんかが流行っていますよね。
あれは明らかにH&N物質を活性化させる運動に思えます。
ドーパミンは悪者ではないですが、
- 幸福をもたらすのはドーパミンではなくH&N物質
- ドーパミンとH&N物質は反比例する
の2点は非常に大切な知識だと思います。
同時には出ないので、ドーパミンを切って、目の前のことを満喫する時間が人生には必要です。
具体的に何がドーパミンを刺激して、何がH&N物質を刺激するのかは、ぜひ本書を読んでみて下さい。
ドーパミンは誰しも当たり前に持っている物質ですから、あなたが興味がある分野にも応用できることがきっと多いでしょう。
本を読んでわかった「スマホ依存の対策」をまとめました

以上、スマホ依存に関する本を紹介しました。
これらの本(だけではないですが)から学んだ「スマホ依存対策」を端的にまとめました。
本当は本をていねいに読んだ方が100倍良いですが(笑)、合わせて参考にしてみて下さい。
関連記事:スマホは人生の無駄になる!無駄に見てしまう対策5選。とにかく離れることが大事です





